
創業期
下請け時代に培われた
確かな技術力
創業者の加藤正平は、愛知県刈谷市で江戸時代から続く材木屋「白半」の五男として誕生し、1940年から木工業を営むようになりました。1947年には、刈谷木材工業株式会社を設立。当時は戦後復興とともに紡績産業が大きな発展を遂げており、豊田自動織機製作所の下請けとして木函やミシンテーブルの木部品の加工などを営んでいました。その後、さまざまな製品の木部品の生産を請け負う中で、板材の乾燥や木の加工技術を培っていきます。さらに、「お客様にご迷惑をおかけしてはいけない」と、お客様のご意見を踏まえ、品質の改善に注力。このとき根付いた「品質至上」の考え方が、現在も理念として受け継がれています。
しかし、次第に、仕事量の増減を予測できない下請け仕事だけで従業員を抱えた工場を続けることに限界を感じるようになり、加藤正平は「なんとかして我々自身の、自社のブランドを持ちたい」と考えるようになりました。そこで目を付けたのが、1959年から日本ミシンテーブル工業組合を通じてアメリカに輸出していた椅子です。3年ほどで生産終了となった商品ではありますが、座り心地の良さには自信がありました。加えて、1955年頃から家具業界がめざましい発展を遂げていたこともあり、木製家具の国内向け生産は将来有望でした。
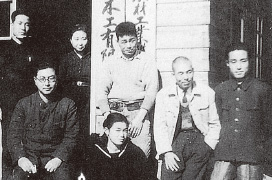

品質至上
創業時から、「お客様にご迷惑をおかけしてはいけない」と、お客様や得意先様からのご意見を踏まえ、品質の改善に努めていました。今日の理念でもある「品質至上」は、この頃から根付いていたと言えます。

ブランド創成期
自社ブランドでの
家具づくりをスタート
1960年代に入ると日本経済の復興に伴い、都市部に人口が集中します。それにともない限られたスペースで生活動線や水回りに配慮した集合住宅が増加し、洋家具のニーズも上昇。当社は対米輸出のソファを手本に、応接間向けの商品開発に着手し、1962年に初の自社商品となる「#1000(カリモク60ブランドのKチェアの原型モデル)」を発売しました。
その後、さらなる品質向上を目指して、椅子の表面を布で張り上げる総張り椅子に挑戦していきます。当時は総張り椅子に必要とされる職人の技量を有していませんでしたが、社員が京都の職人に弟子入りして技を習得。加藤正平が創業時から言い続けてきた「易きにつくな、難きにあたれ」という言葉を体現していきます。
1964年にはカリモク家具販売株式会社を設立し、家具専門工場を新築して洋家具の量産体制を整備するなど、本格的に家具製造卸としての歩みをスタート。社名は刈谷木材工業の「刈」と「木」をとって名付けられました。家具メーカーとしては後発で知名度も低かったため、卸業者から充分な取引をいただけず、自分たちで商品をトラックに積み、商品を直接見せながら商談を進めることで販路を拡大していきました。
また、洋家具づくりを学ぶために欧米諸国を回り、部屋の家具調度品を一つのイメージに沿って整えるインテリアコーディネートの必要性を認識します。この経験を活かし、椅子やテーブル、キャビネットに至るまで同一のデザイン軸でまとめたシリーズ家具を展開するようになりました。専門性を磨けば、品質が良くなり、またコストも下げられるとの考え方から品目ごとに専門工場を整えていきました。


「易き(やすき)につくな
難き(かたき)にあたれ」
加藤正平は創業時から「易きにつくな、難きにあたれ」という言葉で、一見難しいと感じることでも挑戦し、自分たちにできることを増やし続けることの大切さを表してきました。その想いが受け継がれ、当社では技術を一つ一つ磨いていきました。

発展期
日本経済の成長とともに、家具事業を拡大
この時期に経営を担っていたのは、創業家2代目の2人です。論理的な思考を得意とする加藤英二は製造を、人を見て本質を語ることを得意とする加藤知成は営業を担当し、この二人によって当社は大きく飛躍することになります。中でも、当時は他社がやっていなかった、物流網やITインフラを整備し受注時に納期の確約できる体制、全国各地に営業所を開設しセールスと物流が一体となりお客様の要望に柔軟に対応できる体制を構築できたのは大きな成長につながりました。
当時は、女性が家具を嫁入り道具として持参することが多く、婚礼家具と呼ばれていました。家具専門店ではこれが大きな収益源となり、主流だった婚礼タンスに加えて、ダイニングチェアやテーブル、ソファなどが販売されるように。当社ではこの時期に、お届け日を明確に回答できるシステムをいち早く整備し、これにより家具専門店が婚礼家具と当社製品をセットで勧めて頂けるようになりました。お届けミスや遅延が許されない婚礼家具市場における信頼を醸成し、1970年代後半には家庭用の国内木製家具メーカーで売上高トップとなります。
家具売上は伸びていった一方、品質面、デザイン面での伸びしろも散見されてきました。そこでより多くの層のお客様に価値を届けるため、を再び欧米諸国を回って品質やデザインやの作り込みを学びます。その後、1983年に高級家具ブランド「domani(ドマーニ)」を発表。これはロイヤリティ契約を結んだ海外メーカーのデザインを、自社で生産するブランドでした。都内の百貨店をはじめ、全国の主要百貨店およびグレードの高い専門店で展開されていきます。

100歳の木を使うなら、
その年輪にふさわしい
家具を
つくりたい
木が家具に使えるまでに成長するには、短いものでも70年以上、一般的には100年はかかると言われています。当社では木への想いから、80年代後半にテレビコマーシャルで「100歳の木を使うなら、その年輪にふさわしい家具をつくりたい」というメッセージを流していました。

停滞~変革期
停滞期を経て、新たな
ブランドの在り方を模索
1990年代に入ると、バブル景気が終焉を迎えるとともに、新築戸数の減少や晩婚化が家具業界に大きな影響を与えます。団塊世代の住宅取得ピークにあたる1987年には173万戸の新築着工がありましたが、1998年には120万戸となり家具需要の分母が減少。加えて、婚礼家具市場でも、新婚夫婦が自分たちで家具を決めることが好まれるようになってきたため、親が選ぶ前提の婚礼家具の文化は衰退していきました。さらに同時期に収納のビルドイン化も進み、家具専門店は収益の柱をなくし、経営が悪化していきます。
このような状況下でカリモク家具では3代目の世代が中心となって立て直しを図ります。
大量生産、大量消費が基本だった家具業界でしたが、お客様それぞれに応じた製品を作るCOM(カスタムオーダーマイン)を他社に先駆けて仕組化し、さらに椅子やソファの”座り心地”に注目した開発を行うことで、多様化するお客様のニーズに対応してきました。家具は実際に座ってご購入されるお客様がほとんどであることから、座った時の座り心地を科学的に解析し、最適な椅子の高さ、背もたれの角度を算出し、開発に活かしていきました。また、メーカー自らが運営する展示スペースであるショールームを拡大し、より多くのお客様に見て、体験して、価値を感じて頂けるように積極的に働きかけていきました。
一方、木を使い続けることで、森林が枯渇してしまうことを懸念していました。そこで1988年にカリモクマレーシアを設立し、ゴムの木を原料とした循環型の木材資源活用を他社に先んじて進めます。天然ゴムの原料となるラテックス樹脂は、ラバーウッドと呼ばれるゴムの木から採取されます。しかし、木が一定程度まで成長するとラテックスの採取量が減るため、20年程度のサイクルで植林と伐採が行われています。ラバーウッドは腐りやすいため家具用材には向いていませんでしたが、防腐処理を施すことで活用できる技術が、確立された頃でした。そこでマレーシアに工場設備を整え、周辺のゴム農園で伐採されたラバーウッドを家具に活用できるようチャレンジしていったのです。当時は今ほど環境問題への関心は高くありませんでしたが、創業以来木材を扱ってきた経験から、自然と循環型社会に目が向いていました。
この時期、ブランドとはなにか?を考える契機となったのは、2002年に誕生した「カリモク60」です。ナガオカケンメイ氏が提唱する企業の原点に焦点をあてたロングライフデザインに賛同し、カリモク家具の創業時の1960年代から作り続けている家具と当時の商品を復刻。お客様は何を価値と感じて頂いているのか、カリモク家具を創り上げてきた先人たちの家具づくりに対する想いはなにかを、再認識する機会となりました。

商品を常に目の届く
ところで
製造する
1990年代後半、家具専門店では大型化やチェーン展開が進み、デフレ経済に対応すべく、多くの家具メーカーは人件費の抑えられる中国へと生産拠点を移すようになります。しかし、家具は耐久消費財であり、売って終わりではなく、使って頂いている中で出てくる不具合にも誠実に対応し続けることで、お客様から信頼が生まれます。そこまで含めた”品質”を維持するために、当社では国内で最終製品を作ることにこだわっています。

新たな挑戦期
提供価値の多様化&深化
市場ニーズがより多様化していく中、それに対応すべく当社もカスタムオーダーをさらに拡大しました。木材の樹種においては、それまでの国産材中心から、日本に自生していないがお客様の人気が高まっていたウォールナットなどの新樹種を導入し、家具表面の張地にも国内外問わず、品質やデザイン性の高い張地を導入していきました。製造現場では、安全な職場づくり、多品種少量生産に対応できる生産体制を作るため、海外から最新鋭の機械加工設備を導入し、”ハイテク&ハイタッチ”を合言葉に、人と機械の両輪でモノづくりの品質を高めています。さらに、これまでの木製家具製造の技術を活かした、他社とのコラボレーション製品の開発も精力的に取り組んでいます。家具ビジネスにおいては、これまでのkarimokuブランドだけでなく、新たなストーリーを持ったブランドを複数立ち上げています。2009年に誕生したブランド「Karimoku New Standard(カリモクニュースタンダード)」は、国産広葉樹の中でも、これまで家具に使えなかった未利用材を家具とし、その個性を活かしたブランドになっています。バイオマス用のチップ材ではなく、家具にすることで、森林事業者にも利益が生まれ、持続可能な森林経営が可能になります。
さらに2019年にはNorm Architects、芦沢啓治建築設計事務所と共に、ケース(空間)ごとに最適な家具を作る中から生まれた「Karimoku Case(カリモクケース)」を立ち上げました。このブランドには、後にFoster+Partners(Norman Foster)も加わっています。これらの新ブランド開発と積極的な海外イベントへの出展により、海外の木製家具市場でも、カリモク家具のブランド認知を高めています。


木とつくる幸せな暮らし
カリモク家具の原点、それは木工所です。家具製造で業績を拡大してきたカリモク家具ですが、今一度原点に立ち返り、木材を調達し、乾燥して、加工して製品を作ることを通して、お客様に様々な価値を提供していきたいと考えています。その方法は家具に留まりません。生活の中に木がある暮らしを通して、お客様に幸せな暮らしを提供することにこだわり、当社はこれからも進んでいきます。
















